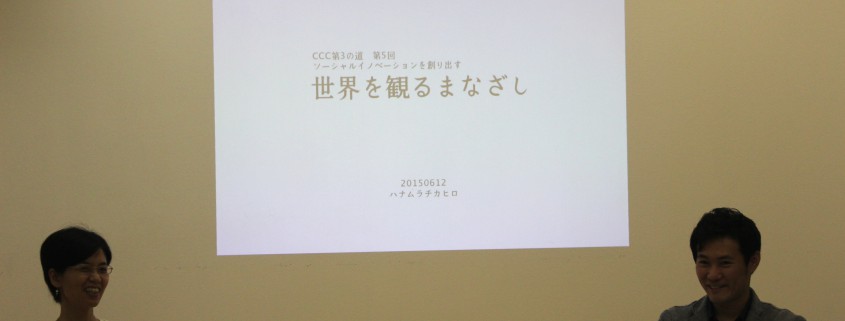
【第三の道】問いを投げかけ、内面を掘り下げるアート 花村周寛(ランドスケープアーティスト)× 由佐美加子
「第三の道」第5回のゲストは、ランドスケープアーティストで大阪府立大学准教授の花村周寛氏だった。花村氏が手がける、見知った風景の中に未知の風景を発見していく「風景の異化」の事例を交えた解説から、なぜいまアートの重要性が増しているのか、そのことと第三の道を探ることの関係性へと、話題は深まっていった。
「主観的、美学的で私を含む」、風景をデザイン
「私は風景のデザインをアートからアプローチしている」と語る花村氏。この言葉をより明確に感じてもらうため、「風景」と「景観」の違いを説明するところから、花村氏は話を始めた。
美学者のアラン・ロジェは、環境は計測できるもので科学的であるのに対し、風景は人の心の問題であって美醜で語られるため、美学的だとしている。また建築家のバックミンスター・フラーは、宇宙とは私を含む全て、環境とは私以外の、私を取り巻く全てだと言う。「環境と宇宙の違いを、そこに私が含まれるかどうかで語ることに注目したい」と花村氏。そして地理学者のオギュスタン・ベルクは、風景は主観的であり、景観は客観的だとしていると紹介した。
こうした先人の定義を参考にしながら、花村氏は「景観とは、客観的、科学的で私を取り巻くもの」「風景とは、主観的、美学的で私を含むもの」と、両者を定義。その上で、「私自身が今日お話しするのは風景のデザインの話です」と語った。
次に「ランドスケープ」という言葉の解説を通じて、花村氏は自身の活動を特徴づけていった。この言葉は「ランド」と「スケープ」でできていると花村氏。「ランド」とは大地や土地、ある場所を指し、「スケープ」はその場所の景、眺めを指している。「シティスケープといえば街の眺め、ウォータースケープといえば水辺の眺めを指すことになります」。このランドスケープという言葉には、眺める対象である場所と、眺めている自分が存在する。「つまり場所と自分の関係性によって、風景は成立するのです」
通常、ランドスケープデザインをするという場合、「ランド」、つまり場所の方をデザインすることが多い。「どんな庭をデザインするのか、どんな建築を景観の中に置くのか」といった具合だ。「この10年私が取り組んできたのは、通常の環境デザインに加えて、風景を眺める自分を変えていこうというアプローチです。自分が変われば風景が変わる。これを『まなざしのデザイン』と呼んでいます」
放置すると固定化する、場所と自分の関係性
風景は場所と自分の関係性の中から生まれてくると先に述べたが、「その関係性は、放置するとどんどん固定化してしまう」と花村氏は説く。新しい場所に引っ越したとき、新しい会社や学校に入ったときには、目にするもの全てが新鮮に映るだろう。「ですが毎日同じ道を通り、毎日同じ人に会っていると、発見は少なくなる。関係性が固定化し、風景が見えなくなるのです」
このように起こってしまう場所と自分の関係性の固定化を、いろいろな手法によって「異化」していく。「異化をすることで、見知った風景の中から今まで見たこともない新鮮な風景が生まれてくるのではないか。それが私の仮説です」。つまり「まなざしのデザイン」は、「風景の異化」を目指しているともいえる。
鉄道模型の人形を、見慣れた風景に置いて撮影
風景の異化に取り組んだ事例として、花村氏は「ガリバースコープ」というワークショップを紹介した。このワークショップでは、87分の1サイズの鉄道模型に使われる人形が多数用意される。この人形を子どもたちに渡し、見慣れた風景の中に自由に人形を置いて、カメラで撮影してもらう活動だ。「人形を置くことで、いつも遊んでいるブランコが巨大な工事現場になったり、墓石が石畳のカフェになったりします」。人形を置いて撮影することで、なじみのある風景の中に、新鮮な風景を生みだしているのだ。
デジャヴュというフランス語は、読者の皆さんもお聞きになったことがあるだろう。どこかで見たことがある感じ、「既視感」という意味だが、これにはジャメヴュという対義語がある。見たことがない感じのことで、「未視感」と訳される。「風景のジャメヴュを起こしていく。これが、私が全体として取り組んでいることです」
「本当にそれは醜いのか?」疑問を投げかける。
ここで由佐は「なぜ花村さんは、まなざしのデザイン、風景異化に情熱を燃やすのですか」と質問した。花村氏は、「芸術全般がやっていることが、実はまなざしのデザインだと考えている」と応じた。たとえば、世間ではずっと醜いとされてきたものに対して、「本当にそれは醜いのか?その中に美や真実が隠されているのではないか?」と疑問を投げかけ、美を抽出して、示していく。「それが芸術家の役割の一つではないでしょうか?」と話した。
更に花村氏は、まなざしのデザインの事例紹介を進めた。次に紹介したのは、2008年、大阪府豊能町で開催された現代アートイベントで発表した、「ニテヒナル」という作品だ。会場となった山の散策路に、約30点の作品を点在させた。地図を片手に来場者は作品があるとされる場所に行くのだが、いったいどこに作品があるのか、わからない。「実は自然の植物の中に、プラスチックの造花を紛れ込ませていました」。何かの拍子に「あれ、これはプラスチックでできている!」と来場者は気付く。「すると来場者は、どれが本物でどれが偽物か、どれが自然でどれが人工なのか、わからなくなってくる。自然の植物を指さして『あれは絶対作り物だ!』と言い出します」。この瞬間、見なれた野山の風景の、異化が起こっているのだ。
次に花村氏は、風景異化の手法の4分類を説明した。「場所を刺激する」か「自分を刺激する」を横軸、「物理的に刺激する」か「心理的に刺激する」を縦軸とすると、4つの象限に分けることができる。まず「場所×物理」による風景異化は、風景を構成する素材を組み替えようとするもので、通常の建築、空間デザインなどが該当する。「自分×心理」は認知や行動の様式(モード)を変えていくことで、「例えばある物事に対して情報の与え方を変えたり、接し方を普段と変えたりということが、この象限に相当します」。主に「自分×物理」の象限にあてはまるのが、「ガリバースコープ」のワークショップだ。「道具を使って自分の感覚をゆさぶるやり方です。このワークショップでは人形やカメラを使って知覚をゆさぶっています」。また「ニテヒナル」の事例は、造花によって「場所×物理」、地図によって「自分×物理」の双方に働きかけている作品だと説明した。
最も強い記号をもつ場所。それは、病院
そして「場所×心理」の象限で取り扱うのが、表象記号であると花村氏はいう。「学校、工事現場など場所にはそれを示す記号がある。それをゆさぶり、異化することで風景の見え方が変わり、人の行動が変わるのではないでしょうか」。場所にはいろいろな記号があるが、中でも人の生死にかかわり、非常に強い記号を持つ場所とはどこか。花村氏は、「私は、病院ではないかと思っています」と語った。その上で、病院という場所は、芸術や風景異化が本当に必要な人たちが集う場所ではないかと問いかけた。「美術館や劇場は、芸術を見たい人たちが行く場所です。しかし本当に芸術を必要とする人がいる場所は他にもあり、そこに手を差し伸べられる可能性があるのではないか」と話し、病院に風景異化を届けた事例の紹介を始めた。
2010年、大阪市立大学医学部付属病院で発表した「霧はれて光きたる春」。「病院にいる全ての人に向けた作品を」という依頼を受けた花村氏が注目したのは、18階建ての病院の建物中央部にある、大きな吹き抜け空間だった。「建築的には、採光のために設けられた空間です。エレベーターホールや廊下に面し、この病院を訪れる人は誰もが目にする空間なのに、誰も注目していませんでした」。そんな空間は潰してしまって、ベッドを増やした方がいいのではないかという声さえ聞かれた。「みんなが無駄、意味や価値がないという空間について、本当にそうなのか?と問いかける。それが、アートの果たせる役割の1つかもしれません」
患者も、医師も、看護師も、空を見上げたる“ただの人”に
この作品では冒頭、吹き抜け下部から人工の霧が立ち上ってくる。その霧が徐々に晴れていき、吹き抜け上部からは大量のシャボン玉が降ってくる。全館放送から音が流れる中、約30分間の神秘的な風景が、日常は誰も注目することのない空間に繰り広げられた。「患者さんも、医師も、看護師も。老若男女みんなが部屋から廊下に出てきて、空を指さしたり、見上げたりする“ただの人”になっていました」
花村氏は記号の強い病院という場所では、こうした共通体験が必要だと説く。「医者は白衣を着ることで医者として、看護師は制服を着ることで看護師として、院内ではそれぞれの役割を演じています」。それは患者も同じで、患者という役割を演じることが求められる。「そういった演技は社会の中で物事をうまく機能させていくために必要なことだが、機能や役割を超えたコミュニケーションの中で、人は救われることがあります」。いつも怖い顔をしていた医師の先生の目が、シャボン玉を前に少年のように輝いているのを見たとき、その人へのまなざしが少し変化する。「業務として話しかけるのではなく、役割や立場や職業の仮面を脱ぎ捨てた人としてのコミュニーション」のきっかけを作ることが大事なのだと、花村氏は語った。
古いまなざしを解体し、新しいまなざしを構築
誰かがまなざしを向けるからそこに風景が生成され、それがずっと当たり前になってくると今度はまなざしが消滅して、風景が消滅する。「風景は生成と消滅を繰り返している」と花村氏はいう。今までのまなざしが消滅して、新しいまなざしが生成することがジャメヴュだ。「それを意図的に起こそうとする風景異化の立場から言い直すと、古いまなざしを解体して、新しいまなざしを構築しているのです」(花村氏)
風景という言葉を「価値」や「意味」、「世界」や「現実」という言葉に置き換えても同じことが言えるのではないかと、花村氏は指摘する。「つまり価値や意味、世界や現実は生成と消滅を繰り返していて、古い価値が解体されて新しい価値が生まれ、古い意味が解体されて新しい意味が生まれる。風景異化とはそれを一度にすることです」
「誤解を恐れずにあえて言うならば、その構築と解体という役割に分解すると、主に構築を担っているのがデザインであり、主に解体を担っているのがアートなのではないか」(花村氏)。デザインとは有用性や機能のあるものを作ることであり、それは何か設定された課題を解決する、ソリューションの行為だと考えられる。それに対して有用性や機能からは自由であるアートは、「何が問題なのかということを投げかけるクエスチョン、つまり問題提起の役割があるように思えます」
デザインは近代的な概念で、それ以前は全部アートだった。「それが近代以降は、有用性の部分はデザインが担うことで、アートは有用性から自由になり、既存の世界の見方やまなざしに対する問いかけを担うように分化していったという見方ができる」と花村氏。「まなざしをデザインするというのは、そういう意味でアートのようなクエスチョンからアプローチして、閉塞した現実に何かの気づきをもたらすことで、ソリューションに至るということを一度にやろうとしています」
宗教とアートも、かつては一体のものだった
「35000年前の洞窟壁画を見ていると、宗教と芸術の起源が同じであることがよく理解できる」(花村氏)。洞窟の奥まった暗がりの中、松明の灯だけで目の前に見えていない狩りの様子を壁面に描くという芸術行為は、極めて宗教的な行為であったに違いない。「宗教やそのもとになる信仰と芸術は、共に人間の精神をめぐる一体的なものであったのが本来の姿。ですが、それが時代が下るにつれて分離していったのです」
根幹にある自我と関係していることだが、人間は孤独で生きていくことが難しい心を持っていて、誰かや何かとつながることを求める。「その根幹に、宗教や芸術という発明があり、それによって個人から宇宙までつながる感覚を担保していた。だが、近年は宗教が崩壊しつつあります」。そんな中、もう一度、「心のインフラ」として芸術の役割を見直す必要がある時代に来ているのではないか。「まなざしのデザインはそんなことと関係している」と花村氏は説いた。
ここで来場者からの質疑応答タイムが設けられた。「現代は宗教だけでなく、アートにも問題があるというお話だったが、アートのどういう部分が問題なのか」という質問が寄せられた。花村氏は「人間の心と美の問題というのは、世界のあらゆる物事と関係しているはず。だが、アートという領域の中の問題だとカテゴリ化してしまうことで、他の問題と関係づかなくなる可能性がある。宮沢賢治が、万人が芸術家になるべきだと言っていたことの中に、固定化してしまった芸術の問題に対する一つの批判を見出しています」と答えた。
「アートとマーケティングは、反対の行為」
「花村さんのアートは、従来のそれとは違うものだと感じる」という感想に対しては、「アートは、商業的なマーケティングとは反対の行為かもしれない。顧客や大衆が欲しいと感じているものに応じて答えを出すというマーケティングに対し、アーティストは他者がどう言おうと、自らが求めるものが何なのかを徹底的に掘り下げていく。その哲学的な探求の過程の中で、人間という普遍的な存在が見えることがあり、それがその人の個人的な問題だけではなく、公共性を帯びることがある。それをすくい上げることが重要なのです」と話した。
花村氏のプレゼンテーションを受け、最後に由佐が発言した。「アートとデザインは一度両者を分けて考え、統合する必要があるという指摘など、人にとってこれが本質だと思える要素が、花村さんの考えの核にあると感じる」といい、その核が現代社会には失われていることを問いたいという思いが伝わってくると指摘。「自らの内面に求めるものを追っかけて行き、外部に表現していく行為がアートだが、第三の道を考えて行く上でも、自分の内面に向かっていくベクトルがとても重要なのだと感じている」と話し、セッションを締めくくった。
花村周寛(はなむら ちかひろ)
1976年大阪生まれ。アートや空間デザインなどを通じて、風景の見方や人と人とのコミュニケーションを変える「まなざしのデザイン」を展開。病院を始めとする公共空間でインスタレーションやパフォーマンスをしている。大阪府立大学大学院生命科学研究科修士課程修了。博士。ランドスケープデザインオフィス、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任教員などを経て現職。俳優として舞台やカメラの前に立つこともある。








